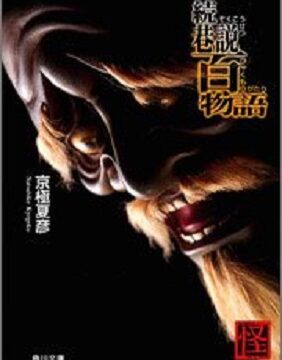小説『ある男(平野啓一郎 著)』の感想レビュー。
あらすじ
弁護士の城戸は、かつての依頼者である里枝から、「ある男」について奇妙な相談を受ける。
宮崎に住む里枝には、二歳の次男を脳腫瘍で失って夫と別れた過去があった。
長男を引き取って十四年ぶりに故郷に戻ったあと「大祐」と再婚して幸せな家庭を築いてていた。
ある日突然「大祐」は事故で命を落とす。
悲しみにうちひしがれた一家に「大祐」が全くの別人だという衝撃の事実がもたらされる・・・。
400文字感想
里枝には、離婚して故郷に戻ったあと『大祐』と再婚し幸せな家庭を築いていた。
娘が生まれて三年後、『大祐』は仕事中の事故で亡くなってしまう。
没交渉だった『大祐』の家族に『大祐』の死を告げ、長男が告別式に来て顔を確認してもらったところ『大祐』は別人だったことが判明する。
里枝は、離婚のときお世話になった弁護士、城戸に『大祐』が別人だったことを相談し、
城戸は『大祐』もとい、xが何者だったかの調査を始める・・・
戸籍を売り買いした男xの半生を追いかける物語。
今までの自分を捨て、名前を変えて生活するのはどんな人生なんだろう?
読み終わった後、自分だったら?なんて考えてしまったけど、現実世界でも似たようなものだった。
ゲームやSNS、当サイトのレンゾーだって偽名を使っている訳だし、相手との関係性もそう。
免許でも確認しない限り、相手の自己紹介が偽名の可能性なんて大いにあり得る。
名前なんて記号でしかないけど、その記号があるから自分や他人を認識できるんだよなぁ。
不思議な読了感でした。
作中の言葉
弁護士だろうとか、日本人だろうとか、何でもそうですよ。
アイデンティティを1つの何かに括りつけられて、そこを他人に握りしめられるってのは、堪らないですよ。
堪らないけど、どこかでは一括りにされちゃうよね。
外国いけば、日本人として一括り、
出身地で一括り、
世代で一括り、
それは嫌がっても避けられないし、事実なんだから受け入れて行動するしかない。
誰も、他人の本当の過去など、知ることは出来ないはずだった。
自分の目の前にいないとき、その人がどこで何をしているのかも。
いや、たとえ目の前にいたとしても、本心などというものは、
わかると考える方が思い上がっているのだろうか。
間違いなく思い上がり。
僕は、他人になるべく期待しないようにしている。
自分が介入できない部分に期待を持つのは辛いから・・・
それでも、あの人は僕のことどう思っているんだろう・・・
とか考えちゃうんだよね。
「僕たちは誰かを好きになる時、その人の何を愛しているんですかね?
出会ってからの現在の相手に好感を抱いて、そのあと、過去まで含めてその人を愛するようになる。
で、その過去が赤の他人のものだとわかったとして、二人の間の愛は?」
「わかったってところから、また愛し直すんじゃないですか?
一回、愛したら終わりじゃなくて、長い時間の間に、何度も愛し直すでしょう?
色んな事が起きるから」
「そうですね。
・・・愛こそ、変化し続けても同じ一つの愛なのかもしれません。
変化するからこそ、持続できるのか・・・」
『一回、愛したら終わりじゃなくて、長い時間の間に、何度も愛し直すでしょう?』
『愛は変化するからこそ持続できる』
このセリフ好き。
同じ愛だけじゃ飽きちゃうもんな。
相手の変化や、自分の観測の仕方によって愛の味わいが変わるから長続きできる。