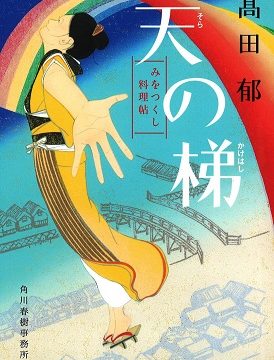小説『星を掬う(町田そのこ 著)』の感想レビュー。
あらすじ
すれ違う母と娘の物語。
小学1年の時の夏休み、母と二人で旅をした。
その後、私は、母に捨てられた――。
ラジオ番組の賞金ほしさに、ある夏の思い出を投稿した千鶴。
それを聞いて連絡してきたのは、自分を捨てた母の「娘」だと名乗る恵真だった。
この後、母・聖子と再会し同居することになった千鶴だが、記憶と全く違う母の姿を見ることになって――。
感想
パートの給料も別れたDV夫に奪われてしまう主人公の千鶴は、自分に降りかかる不幸を全て「あの時、母に捨てられたからだ」と思って生きていた。
お金欲しさにラジオに自分と母との思い出を投稿すると、母の知り合いから連絡がきて、DV夫から逃げ出して母と母の友人たちがすむ住居へ転がり込む。
過去のトラウマが原因で、全てを他者のせいにして、内省しない奴らに本を読んでいてイライラするものの、自分が同じ立場だったら他者のせいにして逃げるのだろうか?
と考えてしまう。
最終的には、傷ついても、立ち上がって前に進んでいくんだけれど、
登場人物たちはいきなりどでかい傷を貰っちゃったので、傷に対する慣れがなく、治るのに時間がかかっているのであった。
作中のことば
「不幸を親のせいにしていいのは、せいぜいが未成年の間だけだ。
もちろん、現在進行形で負の関係が続いているのなら話は別だけど」
「自分の人生を、誰かに責任取らせようとしちゃだめだよ」
「だから、そういうのは十代で整理しておけって。
せめてこの二十代の間でどうにかしたほうがいい。
いい加減、やめな。ていうか君は、あんまりにも幼稚すぎるんだよ」
千鶴が自身の境遇に嘆き、自分の不幸は母のせいだと吐露したことに対しての台詞。
些細なことでも、自分の行動を顧みず、他者のせいにするのは一定数いるよね。
そいういうやつらは、内省しないから進歩しないし、同じようなことを繰り返すんだ。
「君がさっき恵真にいったことは、弱者の暴力だ。
傷ついていたら誰に何を言ってもいいわけじゃない。
自分の痛みにばかり声高で、周りの痛みなんて気にもしないなんて、恥ずかしいと思えよ」
「・・・言い過ぎた。って思って、ます。だから、それは謝った、じゃないですか」
「あれは自分がみっともないって気付いただけの、取り繕いだったろ。
それくらい、自分で分かるんじゃないの?
君ね、そういうところがダメなんだと思うよ。
ひとには誠意だの何だの求めるわりに、自分にはない」
弱者だから何を主張しても許されていると思っている人いるよね。
自覚がなくても、主張している人だって・・・
自分も気をつけなくっちゃ。
加害者が救われようとしちゃいけないよ。
自分の勝手で詫びるなんて、もってのほかだ。
被害者に求められてもいないのに赦しを乞うのは、暴力でしかないんだ
イジメっ子が大人になって当時のことを謝罪する。
ってことに対して微妙な気持ちになる正体が言語化された。
自分が楽になりたいから誤っていただけで、相手の気持ちを考えていなかったんだ。