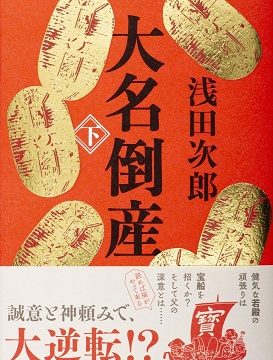『我輩は猫である(夏目漱石 著)』の感想レビュー。
誰もが猫の名前と、冒頭とオチだけは知っている名作品。
あらすじ
物語の語り手は、珍野(ちんの)家で飼われている雄猫。
彼に名前はなく、自分のことを吾輩と呼んでいる。
生まれてすぐに捨てられた吾輩は、生きるために迷走しているうちに珍野家にたどり着く。
家主である中学の英語教師、珍野苦沙弥(くしゃみ)は変人で、胃が弱く、ノイローゼ気味で、なにかと苦労が絶えない。
隣宅の雌猫、三毛子に吾輩は恋焦がれていたが、恋が実る前に彼女は風邪をこじらせて死んでしまう。
この失恋は吾輩にとって大きな経験となる。
その後も珍野家で暮らしながらさまざまな人間と出会う中で、彼は人間や物事を注意深く観察し、哲学するようになる。
脚を4本もっているのに2本しか使わない贅沢さ。誰のものでもない地球を分割して勝手に所有地だと主張するおかしさ。
伸ばしておけばいいのに髪をわざわざ整える不思議さ。猫の視点から見た人間は、実に変な生き物だ。
苦沙弥の元教え子2人の結婚が決まり、珍野家では内祝いが行われた。
吾輩は胃を弱らせた苦沙弥の晩年を思い、死が万物の定めならば、自殺とは賢い行為なのかもしれないなどと考えていた。
悟りに浸っていた吾輩は人間が飲み残したビールを舐めて酔い、水瓶に落ちてしまう。
もがいても爪を立てても水瓶からは脱出できない。
吾輩は抵抗をやめ、自然に身を任せることにした。
「吾輩は死ぬ。死んでこの太平を得る」
彼は水の中に沈んでいった。
感想
執筆当時(1905)の生活風景や風俗を猫視点を踏まえて書かれた小説なんだけど、
当時の当たり前やあるあるネタに馴染みがなくて巻末の補足を見ながら行ったり来たり。
読みづらい上に共感できないという・・・
なんとか読み切ったけど、
当時の常識を補足しながら読まなくてはいけない苦痛のお陰ででしばらく古い小説が苦手になってしまった。
※また読み出すようになるのは三島由紀夫の『命売ります』が面白かったから
序盤は面白かったんだけど、なんか、文章が冗長なんだよな。そこが苦手になったもう一つの部分かも。
表紙の猫が我輩?
読む前のイメージは、和猫だったんだけどな。
本文内でも、
“我輩はペルシャ産の猫の如く黄を含める淡灰色に漆の如き斑入りの皮膚を有している。”
ってある。
表紙は・・・まんまペルシャ猫じゃん!!