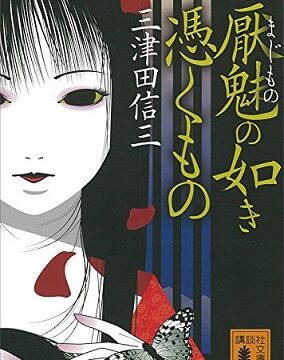小説『仮面の告白(三島由紀夫 著)』の感想レビュー。
あらすじ
生まれつき肌が白く病弱な“私”は、祖母に溺愛され、女の子のように育てられた。
幼少期、汚れた青年の下半身の膨らみを見て、また、彼の仕事を想像し、「私が彼になりたい、彼でありたい」と、胸をざわつかせる。
13歳になった私は、裸の青年が痛々しく縛られた殉教図、グイド・レーニの「聖セバスチャン」を見て、「ただ青春・ただ光・ただ美・ただ逸楽」を感じ取り、興奮する。
そして生まれて初めての射精に至る。
やがて私は、学友の中のひとり、荒々しく、「男らしい」青年の近江に恋をした。
それは明白に、「肉の欲望にきずなをつないだ恋」だった。
懸垂をする近江の格好良さと腋毛の逞しさに目がくらみ、しかし同時に、愛する人に「なりたい・似たい」という感情から嫉妬を覚え、自らその恋を諦めてしまう。
そして私は、女性の裸に興奮する同級生と違う自分は特異な存在なのではないかと、深く傷つき悩み始める。
やがて私は、友人の妹、園子に対して「肉の欲望」のないプラトニックな愛情を抱くようになる。
戦争の最中、徴兵を免除された私は園子と文通を続け、「普通」の男女の恋人を演じた。
そして彼女とキスをしたが、結局何の快感も得られなかった。
自分の性嗜好が「異常」だと確信した私は傷つき、園子の家族からの結婚の申し出を断るのだった・・・
感想
幼少時に、ガテン系の人たちを見て興奮する”私”。
その経験から自分がゲイであるのでは?
と、ひたすら悩みまくる話。
主人公はひたすら自分がゲイがあることを隠す。
隠しつつ悩む。
その心象を楽しむ小説。
・・・楽しめるか?ウジウジ悩みすぎなんだよ!
いや、悩んでいるうちはまだいい。
ゲイだと認めるのが怖くて一般女性にアプローチするのもまだいい。
そして、自分の異常性(=ゲイ)を理解して、結婚を断るのもしょうがない。
なのに偶然に再開した人妻になった園子と密会を重ねる。
女性に性欲が無いからプラトニックな付き合いだけど、
園子の心は揺れ動いて・・・
なんだよこれぇ!?
手放したものがもったいなくなって少しでも手元に置いておこうってか!?
園子が一番の被害者だよ。
性癖なんてものはいくら拒絶しようとしても治らないよ。
もう、認めちゃって、同じ癖を持つ集団に属したほうが幸せだろうに。
現代と違って戦後の当時の同性愛って風当たりが厳しかったのかな?
でも、探せばマイノリティの集団なんて沢山ありそうだけれど・・・
むむむ・・・非常に読みづらい小説だった。
作中のセリフ
下ネタ?をなぜかギリシャ語で書く
・これが私の最初のejaclatio(射精)であり、また、最初の不手際な・突発的な「悪習」だった。
・彼の夥しいそれを見た瞬間からerectio(勃起)が起こっていた。
・私が第二章で、わざとのように、いちいちerectio penis(勃起陰茎)のことを書いておいたのは、
・何人かのephede(青年)の裸体を採集してもちかえるのだ。
東京大空襲の翌日の現場を見て---
恋人を救おうとして死んだ男は、火に殺されたのではなく、恋人に殺されたのであり、
子供を救おうとして死んだ母親は、他ならぬ子供に殺されたのである。
そこで戦い合ったのはおそらく人間のかつてないほど普遍的な、また根本的な諸条件であった。
逃げていれば助かったかもしれないけど、他人を守ったがために・・・
園子との結婚を周りが固めようとしてきたのでなんとか断ろうと考える
(結婚を)断るのなんかわけはない。
接吻だけで責任はないんだ。
「僕は園子なんか愛していない!」
この結論は私を有頂天にした。
愛しもせずに一人の女を誘惑して、むこうに愛がもえはじめると捨ててかえりみない男にわたしはなったのだ。
こうして結婚を断り、しばらくして園子と再会
「・・・それに、僕はあの手紙のなかで、どこにもはっきり結婚できないなんて書きはしなかった。
まだ二十一だし、学生だし、あまり急なことだったからだ。
そうして僕が愚図愚図しているうちに、君はあんなに早く結婚してしまったんだもの」
こいつ・・・クズだな!?