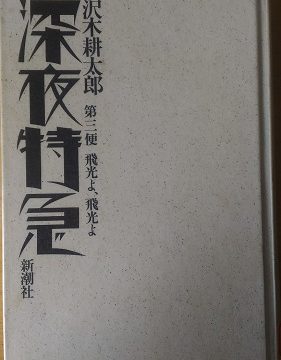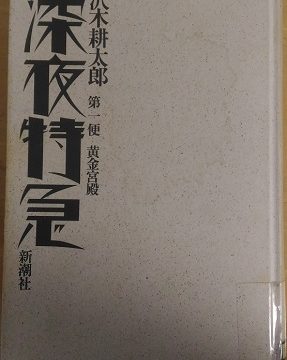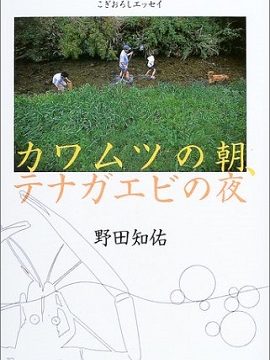『深夜特急第2便 ペルシャの風(沢木耕太郎 著)』の感想レビュー。
【深夜特急第1便】日常にある閉塞感を突破するには外の世界に出よう【沢木耕太郎】
【深夜特急第2便】インドの雑踏を抜けシルクロードを伝いペルシャへ【沢木耕太郎】←イマココ
【深夜特急第3便】アジアからヨーロッパへ旅の終わりに取った行動とは?【沢木耕太郎】
刊行当時の若者たちに刺さり、大量のバックパッカーを生み出したレジェンド本。
その内容は、世界中を身一つで貧乏旅行する旅行本なのである。
もくじ
2巻の行程
カトマンズ(ネパール)
→カルカッタ(インド)→ベナレス(インド)→アムリトサル (インド)
→ラホール(パキスタン)ペルャワール(パキスタン)
→カブール(アフガニスタン)→ヘラート(アフガニスタン)
→テヘラン(イラン)→シラーズ(イラン)→イスファハン(イラン)
第七章:神の子らの家
ガンジーが「神の子」と呼んだ最下層の子供たち。
彼らのための孤児院であり、学校であり、職業訓練所でもあるアシュラムで、私は”物”から解き放たれてゆく・・・
乞食の集団や、
小学生以下の子供の娼婦などインドの地に降り立ちインドの洗礼を受ける章。
インドに行くと人生観が変わる。
なんてことを言う人もいるけど、文字を読むだけで凄いインパクトが伝わってくる
第八章:雨が私を眠らせる
ここカトマンズでは、旅の途中でひとり、またひとりと若者が死んでゆきます。
ハシシを吸い、夢とうつつの間をさ迷いはじめると、恐怖感は薄いヴェールに覆われて・・・
文体が突然変わる章。
妙な敬語で雨が降り続け、部屋に閉じこもり仲間と一緒にハシシを吸う毎日。
鬱屈と諦観が伝わってくる。
ヒッピーたちが放っているすえた臭いとは、長く旅をしている無責任さから生じます。
彼はただ通過するだけの人です。
強この国にいても明日にはもう隣の国に入ってしまうのです。
どの国にも、人々にも、まったく責任を負わないで日を送ることができてしまいます。
しかし、もちろんそれは旅の恥は掻き捨てといった類の無責任さとは違います。
その無責任さの裏側には深い虚無の穴が空いているのです。
深い虚無、それは場合によっては自分自身の命すら無関心にさせてしまうほどの虚無です。
第九章:死の匂い
ベナレスでは、命ある者の生と死が無秩序に演じられている劇場のような町だった。
私はその観客として、日々、遭遇するさまざまなドラマを飽かずに眺めつづけていた・・・
虚無に飲まれまいと飛び出したものの、風邪を引いてしまい瀕死の状態に。
風邪が治り、ある日、ガンジス川のほとりで死体を焼いたり、川に流したりをぼんやりながめていた。
死が身近にある場所で、時間があるがゆえに考えてしまう・・・
気持ち、分かるなぁ
第十章:峠を越える
パキスタンのバスは凄まじかった。
猛スピードで突っ走り、対向車と肝試しのチキンレースを展開する。
クレイジー・エクスプレスに乗って「絹の道」をアフガニスタンへ・・・
私がザックを背負い、いくらか前屈みになりながら歩いていくと、
向こうから、同じように汚いザックを背負い、前屈みになって歩いてくる若者がいる。
どこのだれかはわからないが、西からシルクロードを東に下り、まさにいまインドに入ろうとしていることだけは確かなのだ。
(中略)
彼は、これから私が向かおうとしている道の国々を通過してきたのだ。
そう思うと、親愛の情bかりでなく、畏敬の念までが湧いてくる。
(中略)
彼にとって私は、東から西へ、それもいささか恐ろし気なところにあるインドを通り抜けてきた、いわばインドからの生還者なのだ。
彼の眼にも、親愛と畏敬の念がないまぜになったようなものがうっすらとだが滲んでくる。
だからといって立ち止まりなどせず、ただ互いに顔を見合わせ、口元を綻ばせ、すれ違う瞬間にどちらからともなく声をかける。
「「グッド・ラック!」」
そう言ってから、私は口の中で小さくつぶやく。
達者でな、と。
同じ旅をする同士って感じの心温まるやりとり。
第十一章:柘榴と葡萄
ヒッピー宿の客引きをしながら、断食明けのカブールに思わぬ長居をしてしまった。
そんな時、日本から届いた一通の手紙が弾みとなって、私は更にテヘランへ向かう・・・
翌朝、外に出て驚いた。
一夜明けると、カブールの町も人も、打って変わった晴れやかな表情をしていた。
空は澄んで蒼く、大気は乾いて冷たく、陽光は眩しいくらいに明るい。
雲のかけらもない空には凧が浮かんでいる。
年に何回あるかないかの素晴らしい朝ってあるよね。
それがラマダン(断食)開けの朝だとしたらなおさらだよ。
その時、彼の嫌悪感の根っこにあるものが理解できたように思えた。
彼には、無為に旅を続け、無為に日々を送っているかに見える私のような存在が、たまらなく不快だったのだ。
旅人ってある意味、金持ちの道楽に写ってしまうのかもね。
一生懸命生きている人から見ると、不快感そのものなのかも。
乗客のほとんどは奔放な旅を終え、故郷のヨーロッパへ帰ろうとしている者たちだ。
一日早く帰ったからといってそれが何になるだろう。
むしろ、早ければ早いほど、青春そのものといった日々から足早に遠ざかってしまいそうな気がする。
それらの日々は必ずしも自由で甘美なばかりではなく、多くは過酷ですらあったろうが、いざ失う日が近づいてくると、たまらなく貴重なものに思えてくる。
故郷で待っているのは「真っ当な生活」だけだ。
それも悪くはないが、自分がそのような生活に復帰することができるのかどうか、不安がないわけではない。
復帰できたとしても、果たして「真っ当な生活」に耐えていけるだろうか・・・
旅を、非日常を続ければ続けるほど日常に戻った時の反動って大きそうだよね。
第十二章:ペルシャの風
イランの古都イスファハンで、「王のモスク」を吹き抜ける蒼味を帯びた風の中に、
老いてもなお旅という長いトンネルを抜け切れない自分の姿を見たような気がした・・・
私はあの若者を見捨ててしまったのではないか。
助けを求めているのに、それを無視して置き去りにしてしまったのではないか・・・
あれは単なる行きずりの人にすぎないのだ。
そう思おうとするのだが、明らかに彼は私を頼ろうとしていた。
私はそれを分かっていながら黙って出てきてしまった。
どうせ置き去りにするくらいなら、初めから何もしてやらなければいいのだ。
そう思った瞬間、私は自分がいつもあのようにして人から離れてきてしまったような気がして、さらに暗い気持ちになった。
それでも、少しでも手助けした訳だしさぁ・・・
最後まで面倒みようとすると大変な場面だってあるさね。
いや~、ハッとさせられる文章が多くなってまいりました。
3巻へつづく・・・
【深夜特急第3便】アジアからヨーロッパへ旅の終わりに取った行動とは?【沢木耕太郎】